日本企業がベトナムおよび東南アジア市場へ進出・拡大する際の利点と課題(2025年5月アップデート)
日本企業の世界進出へ 東南アジア

2025年4月30日に石破総理大臣が東南アジア訪問から帰国されました。訪問国はたったの2か国です。ベトナムとフィリピンでした。ご多忙で仕方なかったことは十分理解できますが、それでも、もっとインドネシア、タイ、マレーシア等、なによりも、東南アジアを飛び越えて、中国とインドへも回るべきだったと思いました。
インド・ベトナム市場の重要性と成長:世界的な供給網の再構築がもたらす新潮流
アップル製品と言えば、裏面に「Designed by Apple in California. Assembled in China.」とあることがほぼ当たり前となっていましたが、トランプ政権によりそれが変わりました。
「Designed by Apple in California. Assembled in India.」
「Designed by Apple in California. Assembled in Vietnam.」
グローバルな製造業の中心地といえば、長年にわたり「世界の工場」としての地位を確立してきた中国が挙げられます。しかし近年、この構造に大きな地殻変動が起きています。特に、米中間の緊張と関税政策による影響を受け、世界的な大企業が生産拠点の再構築を急いでいます。その中でも注目されるのが、ベトナムとインドという二つの新興大国です。
Apple社の戦略転換が示す明確な潮流
2025年5月、Apple社のティム・クック最高経営責任者(CEO)は投資家向けの説明会において、米国市場向けのiPhoneの大半をインドで生産し、iPadやApple Watchなどはベトナムが主要な生産拠点となることを明言しました。
「今後、米国で販売されるiPhoneの大多数はインドで製造されることになる」と彼は述べており、ベトナムについても「iPad、Mac、Apple Watch、AirPodsなど、米国向け製品のほぼすべての製造を担う中心地になる」としています。
これは単なる生産拠点の変更ではなく、世界経済における構造転換の一端です。これまでApple社は、「iPhoneのような複雑な製品は中国以外では作れない」としていたにもかかわらず、ここに来て完全な方針転換を図っているのです。背景には、トランプ政権による高額な関税措置と、それによるコスト増(1四半期で約9億ドルの追加コスト)という現実があります。
なぜインドとベトナムなのか?
この二国に共通するのは、以下のような経済的・地政学的な魅力です:
労働力の安さと質の高さ:特にベトナムは、中国に次ぐ熟練労働者を有し、インドも人口構成の若さという強みがあります。
政治的安定と国際協調姿勢:ベトナムは複数の自由貿易協定(FTA)を活用し、欧米市場への輸出拡大に成功しています。
巨大な国内市場:インドは既に14億人を超える世界最大の人口を抱え、今後の内需拡大が確実視されています。
政府の積極的な誘致政策:両国とも外資誘致に積極的で、インフラ整備や税制優遇などを通じてグローバル企業を支援しています。
つまり、インドとベトナムは、「ポスト中国」時代における新たな生産・成長拠点として、明確な地位を築き始めているのです。
ベトナムとインドを見据えた日系企業の戦略的意義
こうした潮流は、単なる製造業だけにとどまりません。IT、物流、建設、医療、教育、小売など、幅広い産業分野においても、両国は新たなビジネスの最前線となりつつあります。
特にベトナムは、2010年代に日本企業の進出ブームが起きて以降、今やサプライチェーンだけでなく、消費者市場としての魅力も高まっている点に注目が必要です。一方、インドはこれまで「難しい市場」と言われてきましたが、最近ではスタートアップやデジタル関連の活況を背景に、若年層消費者を中心に大きな変化が起きています。
したがって、日本企業がこの両国への進出を「単なるリスクヘッジ」や「コスト削減」の視点で捉えるのではなく、中長期的な成長戦略として、積極的かつ先手を打った市場開拓を行うべき段階に入っていると言えるでしょう。
変化に備え、未来に打って出る
グローバルサプライチェーンの再構築が進む中、企業の意思決定において「どこで作るか」「どこで売るか」という問いはますます複雑かつ戦略的な要素を含むようになっています。
Apple社のような世界的企業ですら、地政学的な不確実性やコスト圧力の前では、生産体制を根本から見直さざるを得ません。ましてや中小規模の企業にとっては、今後数年間の拠点選定が、その後の10年の命運を分ける可能性すらあるのです。
ベトナムとインド。この二つの国は、まさにそのような意味で、これからの国際ビジネスにおける「キープレーヤー」となり得る存在です。日本企業にとっても、ただ流れに乗るのではなく、能動的にこの変化を読み解き、主導権を握って未来を切り拓く視点が求められていると感じています。
さて、弊社は展示会出展サービスで、日本でも多くの内資外資企業様をサポートし、ビッグサイトや幕張メッセの現場にいる機会があります。ここ5,6年で、IT系やAIの開発といった展示会で、ベトナムの企業が多く出展してきてます。
中国大陸や台湾の企業と同じくらいか、それより多い印象もあります。ここ10年間で、日本はスマホ周り、ドローン、IT系はほぼ中国に追い越されてしまったと感じますが、同じことがベトナムや他の東南アジアでも5,6年で、まさに起こってきています。そして、スパイアプリなどの報道が多い中華系でないことを売りにしているところもあります。
日本国内の消費市場が少子高齢化の影響を受けて伸び悩む中、成長著しい東南アジア(以下SEA)地域、特にベトナムは、今や多くの日本企業にとって極めて有望な新興市場となっています。
しかし、進出・拡大にあたっては、魅力とともに注意すべきリスクも存在します。本記事では、2025年時点の最新の経済情報や米中貿易摩擦(特にトランプ大統領による関税政策)の影響も踏まえながら考察します。
なぜ今までも、そして、これからもベトナム・東南アジアなのか?
1.経済成長の持続と消費市場の拡大
2024年のベトナムの国内総生産(GDP)は前年比7.09%成長と、過去10年間で最も高い水準のひとつとなりました。これは製造業や不動産、サービス業の好調が背景にあります。2025年も6.8%、2026年には6.5%の成長が予測されており、今後も中長期的な成長が見込まれています。
ベトナムに限らず、インドネシアやフィリピン、タイといったSEA諸国も中間層の拡大が進んでおり、個人消費の成長が続いています。日本企業が新たな消費者層を獲得するには絶好の機会と言えるでしょう。
2.不動産・インフラ市場の活性化と企業誘致
2024年のベトナム不動産市場では、特に北部地域におけるコンドミニアム(分譲マンション)の供給が大幅に回復し、新規供給戸数は30,000戸を超えました。価格も前年比で26%〜36%上昇しており、旺盛な住宅需要が確認できます。
工業団地の土地取得も活発化しており、製造業向けの施設賃貸需要も過去3年間で最も高い水準となっています。これらは製造拠点の分散を目指す企業にとって大きな魅力です。
加えて、政府によるインフラ投資が加速しており、新たな高速道路、空港、ロジスティクス拠点の整備が進んでいます。これはサプライチェーンの安定化にも寄与します。
3.米中貿易摩擦による「チャイナ+1」の追い風
アメリカが中国製品に対して高関税を課す中、多くのグローバル企業は中国依存から脱却する「チャイナ+1」戦略を採っています。その有力な代替地として、ベトナムや東南アジアは注目を集めています。
たとえば、アメリカが2025年中頃にベトナムの一部輸出品(家具、衣料、靴など)に20%の関税を課す可能性が報じられていますが、電子機器などの主力輸出品は比較的安定しており、全体的には依然として投資先として有望です。
4.電動モビリティ(E-mobility)分野の成長ポテンシャル
ベトナム政府は2050年までにカーボンニュートラル達成を目指しており、その一環として交通部門の電動化を積極的に推進しています。特に二輪車の電動化(E-2W)やEVインフラ整備が今後の注目分野です。
2030年までにEVの販売台数は年間150万台に、2050年までには年間730万台に達すると見込まれており、EV関連のサプライチェーン全体に新たなビジネス機会が生まれると期待されています。雇用創出も含め、日本の自動車部品・エネルギー・インフラ関連企業にとって新たな成長市場となるでしょう。
5.現地政府の柔軟な政策対応
ベトナム政府は低い財政赤字と低金利政策を背景に、積極的な財政出動が可能な状況にあります。これは不測の経済ショックにも柔軟に対応できる体制であることを示しており、進出企業にとっては安心材料のひとつです。
進出の際に注意すべきリスク
1.政策変更・貿易障壁リスク
ベトナムは開かれた経済を志向している一方で、米国や中国、欧州連合との貿易摩擦、関税政策の変更など、外部要因の影響を大きく受けます。今後のアメリカ大統領選や地政学的リスクによって、輸出環境が不安定になる可能性も否めません。
2.金融システムの未整備と信用リスク
金融セクターでは、企業グループと銀行の密接な関係がリスク要因とされており、制度改革の途上にあります。企業にとっては資金調達に時間がかかったり、信用調査が難しいといった課題があります。
3.エネルギー供給と価格の不安定性
電力供給においては、再生可能エネルギーの導入が進められているものの、送配電インフラや価格制度の整備が遅れている部分もあります。生産拠点を設ける企業にとっては、停電や価格変動のリスクに備える必要があります。
4.競争激化と人材確保の難しさ
ベトナム市場にはすでに韓国、中国、欧州などの企業が積極的に進出しており、特にホーチミンやハノイでは優秀な人材の確保が難しくなっています。給与水準の上昇も進んでおり、人件費の優位性は徐々に薄れつつあります。
東南アジアの「真の姿」を見極める
日本では、業務スーパー(神戸物産)の店舗で見かけるベトナム産やタイ産のスナックや冷凍食品だけを見て、そして、たまに店内に掲示される製品リコールリストを見ながら「東南アジア=低価格・たまに低品質(ちなみに、弊社は業務スーパー好きで、よく利用しています)」と誤解されている方も多いかもしれません。
しかし実際のベトナムやSEAの現地市場は、それ以上の可能性に満ちあふれています。現地の富裕層・中間層は高級ブランドや機能性商品への関心も高く、現代的なショッピングモールやEVスタンドが都市部を中心に急速に整備されています。
今こそ、真剣に検討すべき成長戦略
日本企業にとって、ベトナムおよび東南アジアは、もはや「安い労働力を求めた生産拠点」ではなく、「中間層の成長をターゲットにした消費市場」かつ「技術移転とイノベーションの共同拠点」へと進化しています。
進出・拡大を検討する際は、魅力とリスクを冷静に見極めた上で、現地パートナーとの信頼関係を構築し、中長期視点での投資計画を立てることが重要です。
ベトナム及び東南アジアの成長ポテンシャルについて、アクションに起こすタイミングがきているかもしれません。
お勧めの記事:
- 海外展示会出展支援
- パナマ法人登録・設立業務
- パナマ船籍登録業務
- パナマ運河の改修の影響
- 信頼の高い海外進出支援サービス
- 東南アジア市場進出支援
- ラテンアメリカ市場進出支援
- EU市場、ドイツ市場進出支援
出展:World Bank East Asia and Pacific Economic Update 2025, 外務省 政府開発援助(ODA)国別データブック
【免責事項】 本ウェブサイトで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。本ウェブサイトで提供した内容に関連して、ご利用される方が如何なる不利益等を被る事態が生じたとしても、弊社は一切の如何なる責任も負いかねますので、ご了承下さい。
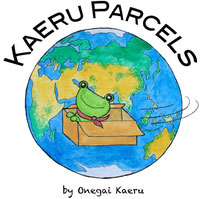
Write a comment